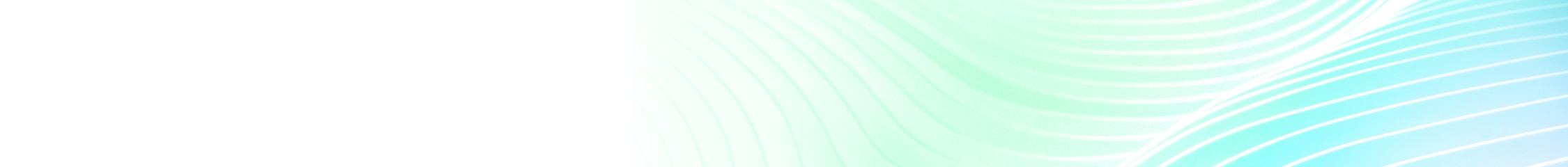栄養治療における看護の役割
栄養は健康の維持、疾病の予防と回復促進など重要な役割があります。超急性期から急性期、回復期、リハビリテーション、療養型から在宅まで、最適なコンディションを維持するために栄養が重要となります。私と栄養治療の出会いは、2003年頃に遡ります。当時、集中治療室で勤務し、重症患者の治療と看護に携わっていました。重症患者が回復する上で、回復の妨げとなるのが合併症です。そのうち最も重要な合併症が感染性合併症と身体機能の低下です。この合併症を予防するのが早期の栄養管理の開始と、場面や状況に応じた適切な栄養配分や栄養量の調整です。2010年に本学会に入会し学会参加や発表を通して多くの学びを得ることができました。看護は様々な場面で提供されることから、看護師が栄養の基礎を学び、さらに栄養治療を理解することは質の高い医療の提供に繋がります。具体的な栄養治療における看護師の役割として、患者の栄養を継続的に評価し適切な栄養コンディションを維持できるようサポートすること。適切な栄養コンディションを維持できるような栄養量、栄養素配分、投与経路の提案や調整、栄養治療における合併症の予防があります。さらに栄養治療だけではなく、リハビリテーションや精神的なサポート、ライフステージに応じた援助を調整するのも看護師の役割です。
栄養を学ぶということは自身の栄養を学ぶということにも繋がります。自分自身が不健康では健康に問題を抱えている患者さんに指導しても説得力が弱くなってしまいます。また日本人の平均寿命は男性81.4歳、女性87.4歳と年々延びています。その一方で介護や病気による制限なく健康に過ごせる期間である健康寿命は、男性72.6歳、女性75.3歳となっています。つまり男性では8.7年間、女性では12年間が何かしらの介護が必要な年数となります。この健康寿命を短縮する最大の要因が生活習慣病です。生活習慣病の背景にあるのが食と運動習慣です。40、50代の食と運動習慣が50、60代の身体の礎となり、やがて迎える70代の健康寿命期間を左右します。
本学会での栄養治療の学びを臨床や自身の栄養として活かし、学会参加や発表そして後進の育成に役立てていただければ幸いです。
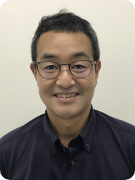
2025年4月1日
看護師部会 部会長
ヴェクソンインターナショナル株式会社
事業デザイン部 課長
清水孝宏